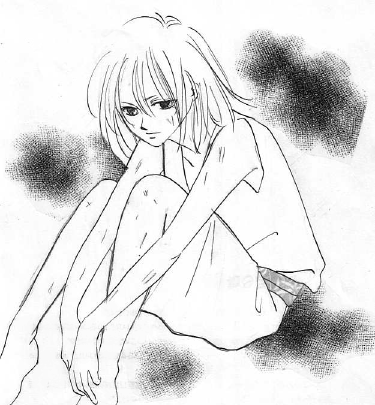道満は、さらに一歩、友雅に近づいた。
友雅は、一歩退きそうになるのをなんとかこらえた。
あらためて向き合ってみれば、道満はいっそうよるべなく、か細く見える。こんな相手を殴ったかと思うと、相手が誰であれ嫌な気分だ。
それでいて、小さな体から発散される気迫の、なんと威圧的で暴力的なことだろうか。
道満はまた一歩近づく。友雅は太刀の柄に手を伸ばした。
道満は怖れもせずに、くくっと笑った。
「?!」
つかもうとした太刀の柄は、いつの間にか黒い蛇の姿に変わっていた。蛇は友雅の手首に巻きつき、鎌首をもたげて友雅を威嚇している。
「…どのような術かわからないけれど、いい趣味をしているね」
「かわいげのない奴だな。もっと怯えろよ」
「真冬の蛇など、滑稽で哀れなだけだよ」
友雅が言った途端、蛇はぴくりと動きをとめた。
「今夜は特に冷えるしね」
蛇は冬の夜気に戸惑ったように力を失っていく。そうして友雅の手首から、力なくぽたりと落ちた。
「ほう…」
道満は感心して友雅を見やる。
「咒の根本がわかっているようだな。あるいは、よほど頭の中身が現実的なのか」
「自分でも心外だけど、たぶん後者かな」
そう、太刀が蛇にかわるなど、そんなことはあり得ない。だから怖ろしくもない。地面に転がっている蛇も、本当は太刀のはずだ。
が、地面にあるそれは、依然蛇のままだ。友雅の力では、道満の咒を完全に解くことはできないと言うことなのだろう。
(咒というのも難しいものだね)
「――やはり面白い男だな。橘友雅…」
道満は嬉しそうにつぶやいた。
「お褒めにあずかって嬉しいけれど、禁城に入りこんだお前を見逃す気はないね」
遠くから管弦の音が流れてくる。友雅たちからたいして離れていない場所で、帝や有力な貴族たちが一堂に会しているのだ。
道満のねらいは彼らだろうか?
「禁城とはな」
しかし道満はけだるそうに苦笑して、管弦の音が聞こえてくる方へ顎をしゃくった。
「あんな輩をつついたところで、なにが面白いのだ? くだらん。――見ろ、この広大な宮城を。あの帝とかいう奴がいなければ、天もまともに動かぬとでも言いたげな、ご大層な建物ではないか。失笑を誘われこそすれ、面白いとは思わぬな」
辛辣きわまりないことを、さらりと言ってのけ
「まぁ、あらゆる思惑が渦巻いているという意味では、面白い場所ではあるがな。歓喜、憤怒、悲哀、享楽――それすらもくだらぬ小者どもの世迷いごとだが、たまに、こちらの気を惹くような強い妄執を放っている奴もおる」
と、さらに傲慢に付けくわえた。友雅は不快を感じる。
「お前はそんなことを楽しんで、気をまぎらすのか」
「――お前が儂にそれを言うなよ。橘友雅」
道満は呆れたように友雅を見た。
「お前だって同じだったのではないのか。人生のすべてに退屈して。そうしていっときでも気のまぎれるものを求めてきたのだろう。儂も同じさ」
道満は、自分の小さな体を見おろす。
「ただ、儂はこの姿だからな。お前のように女を抱いて気をまぎらすことができなかっただけだ」
「…」
「ふふん」
道満は顔をあげて、相手を呑みそうなほど深い目で友雅を見つめた。それは、泰明の、あるいは晴明の瞳を彷彿とさせた。
「――儂はな。荒ぶる神に捧げられた供犠だったのさ」
道満は言った。
どこか遠くで、篝火にくべられた木がはぜる音がした。
「…供犠? 贄のことか」
「そうとも。土地の悪い気に、人や獣の恨みや悪意が引きよせられて悪神となった。その神を鎮めるために、覡(かんなぎ)であった儂が捧げられたのだ。もう儂自身でさえ記憶のあやふやなほど、遠い過去の話だがな……」
道満の大きな目が、昔を思いだそうとするように細められた。その表情は道満の幼い姿とはそぐわなくて、ひどく不気味だった。
「数年ごとに捧げられた供犠たちは、みな発狂するか死ぬかしていた。儂だけが生きながらえたのだ。まぁ、神の陰の気に穢れて、ただではすまなかったがな。だが必死で生きのびた儂に、部族の者どもがどんな仕打ちをしたと思う?」
友雅は答えなかったし、道満も明かさなかった。
今となってはどうでもいいことなのだろう。その目には、恨みなどなかった。ただ、虚無と退屈だけがある。
世界のすべてをのみこんでもなお満たされることのない、底なしの穴だ。
道満は、薄く笑った。
「もう昔の話だ――だが同じようなできごとは、なんどでも繰りかえされる。人は学ばないのだ。学ぶ前に、死んでしまうからな。
すべてはかりそめだ。悦びも恨みも移ろいゆく。その無常の中で、儂と晴明だけが残るのだ」
友雅と道満は、しばらくそのまま対峙していた。
「――…だからお前は、晴明様を欲しているのか」
泰明を亡き者にしようとしてまで。
「晴明は儂の知るかぎり、この国でただ一人の儂の仲間だ。儂だけが晴明を理解できる。あいつの苦悩もな」
「晴明様には心の通じあったご家族がいらっしゃる。お前の出る幕などないね」
友雅は冷ややかに切りかえしたが、道満は鼻で笑った。
「吉平も吉昌も、晴明を救えぬ。なるほど、奴らはほんの幼いころから晴明を救おうとしてきたさ。だが奴らの愛情こそが、逆に晴明を追いつめている。お互いそれに気づいているが、どうしようもできぬ。
泰明の存在もまた、晴明を本当には救わぬ。晴明自身が己の陰の穢れを克服せぬかぎり、晴明と泰明は互いに離れることはできぬのだ。そして穢れというものは、本当は、けっして消え去るものではない。たとえ今回生きながらえても、泰明はこの先も、お前でなく晴明を選びつづけるだろうよ」
友雅は痛いところをつかれた気がして、思わず眉をひそめた。
晴明が危機に際したとき、泰明は友雅のことをふり返りもせずに、ただ晴明のことだけを案じて走っていた。
この先も、たとえ友雅と泰明の仲が深まっても、同じことが起こるのだろうか。友雅はあくまでも、『晴明の次』なのだろうか――
「あきらめろ、橘友雅。お前は人形に心をかけてしまったのだ」
晴明に対して言ったときと同じような、ほとんど優しいと言っていい口調だった。
友雅は優雅に扇を開く。
「…私は欲張りなのでね。泰明が晴明様をいちばんに考えるというなら、晴明様ごと私のものにしてしまうまでだよ」
優しい泰明。自分が愛しく思うのは、あの無垢で不器用な泰明なのだ。泰明が晴明のことをいちばんに想うのなら、それでもかまわない。泰明にとって大切な晴明を、友雅も大切にするまでだ。
自分が報われたいわけではない。ただ友雅は、泰明の優しさが報われるのを見たかった。
「――晴明を癒すと言うのか。お前がか?」
「まさか…そんな大それたこと。そこまで思いあがってはいないよ」
友雅はぱちりと扇を閉じた。
「けれども、晴明様はお強い方だ。私はそれを信じているよ」
「…」
「泰明も晴明様も、お前には渡さない」
道満は黙ったまま、友雅を見つめていた。
やがて、ゆっくりと、唇をゆがめた。
「……はは…はははは!」
女のようになめらかな喉をのけぞらせて、道満は哄笑した。心の底から楽しそうに。
「やはりお前は面白い男だな、橘友雅! この儂に向かって、ようも言えたものだ。冷めていると聞いていたが、なんのなんの」
「最近、宗旨替えしたんだよ」
友雅が婉然と微笑んで言うと、道満はいっそう高らかに笑った。
「いいぞ――そうとも、そうでなくてははるばる京までやってきたかいがない。せいぜい儂を楽しませろよ、友雅!」
「さて。悪いけど、その機会はもうないかもね」
友雅は道満に手を伸ばした。太刀はなくとも、道満をこのまま見過ごすつもりはない。
だが道満は動揺もせず、ひらりと身を翻した。
「待て!」
友雅は道満を追おうとする。
突然、闇の中から長い手がぬっと伸び、友雅の手首をつかもうとした。友雅はとっさに、手にした扇でその手を払いのける。そしてそのまま、閉じた扇の柄を相手の目があると思われる位置に向かってつきだした。
相手は怖ろしく俊敏に扇をよけ、とびのいた。
背の高い、大剣を背負った少年。友雅にも見覚えがある。那由他だ。
那由他は友雅を不穏な目つきで見つめていた。
「…あんた、道満様を殴ったやつ?」
「え?」
「同じ薫りがする。道満様に残ってた薫りと――」
「那由他!」
道満がすっと近づくと、那由他は心得たように道満を抱きあげた。道満は那由他の首に手を回す。
「那由他。こいつは殺すな。儂を楽しませてくれる奴だ」
言われて、那由他はきゅっと唇を引きむすんだ。
「今日はこれで帰るぞ。さ、行け」
打てば響くように、那由他は背後の闇に飛びこんだ。
「!待て」
しかし友雅が建物の陰に回ったときには、誰の姿もそこにはなかった。頭上の屋根の上から、微かに音が聞こえた気もしたが、それもすぐに遠ざかった。
かわりに、別の方向から人の気配がする。内裏内を巡検する近衛府の宮人だろうか。
そもそも友雅は道満の存在を内裏に知られたくなくて、人目を避けて内裏を退出しようとしていたのだ。道満たちを見逃すのは不本意だが、彼らが人に見られてしまってはもともこもない。だいいち、一介の宮人が太刀打ちできる相手とも思えない。
友雅は小さくため息をつくと、身を低くして、あらためて麗景殿へ向かう。
途中、自分の太刀を拾うことも忘れなかった。
そのころ晴明は、冥府の一歩手前にいた。
冥界。黄泉の国。九泉、九原とも言う。さすがの晴明も、そちらがわへ足を踏みいれれば戻ってくることはできない。その手前に来るだけでも大変なことなのだ。
晴明はあたりを見渡した。
漠々とした、荒野だった。どこまでも平らな、灰色の不毛の地。がらんとした空が、そのうえに広がっている。
遠くに泉が見える。色の乏しいこの世界で、ただひとつ、その碧色が鮮やかだった。
(これが黄泉…?)
黄泉の手前までには、これまでにも何度か来たことがある。だが黄泉やその手前は、本来、きまった形や姿があるわけではない。今、晴明が目にしているのは、泰明にとっての黄泉とその手前の世界だった。
泰明の深層の意識や思いが、そのまま反映されている世界でもある。泰明の心象風景であり、言い方を変えれば、泰明自身の世界だ。
(………………うぅ〜ん………なんだかなぁ。泰明〜〜……)
たしかに『黄泉』と教えてやったが、なにもない荒野に泉があるだけという、そのまんまの絵面はなんだ。なんという乏しい想像力か。
これで泉の色が黄色だったら笑ってやったところだが、ごくごく現実的な碧色というのは、それもまた想像力に欠けている気がして、中途半端に笑えない。
泰明らしいと言えばらしいが。
ただ、殺風景なりに美しい世界であることに、晴明はほっとした。
かつてある貴族の命を救うために同じように黄泉の手前を訪れたことがあるが、どんよりと淀んだ空気が重いうえに硫黄の臭いがきつくて、さんざんだった。
けれど泰明の世界は、どこまでも透明で、静謐だった。
柔らかな黄灰色の大地、同じく淡い青灰色の空。それが遙かに遠い地平線で、銀色に混じりあっていた。太陽は見えなかったが、あたりは充分に明るい。影が見えないせいか、大地と空がほのかに発光しているような、そんな風にも見える。
秋の朝のようなひんやりと心地よい空気が晴明をつつむ。
泉は、遠くからでも満々と水をたたえているのがわかった。色から見て、そうとうに深いとも思われる。おそらくは、あの泉の底が黄泉につながっているのだろう。
(だとしたら、泰明があの泉に入る手前で引き戻せばいいはずだけど…)
黄泉の手前で迷っているはずの泰明の姿が見えない。こんな、なにもない荒野で。
泰明が、既に黄泉に行ってしまったはずはない。それは泰明が死んだと言うことだが、泰明がまだ生きていることは、晴明にははっきりと感じとれる。
だったら、この世界のどこかにいるはずなのに。
(泰明――どこ?)
晴明はとりあえず、泉に向かって歩みだした。どうせこの世界には、泉しか目印らしきものはない。
近づいてみると、泉は深い底の小石まではっきりと見えるほど澄んでいた。最奥には暗い洞窟がある。あの中が黄泉か。
念のために、晴明は縁に近づかないようにして泉の中をのぞきこんだ。もしや泰明が横たわっていないかと思って。だが、あまりに澄んだ水に、宙に浮かぶように見える魚がいるばかりで、泰明の姿はなかった。
しかたなく、晴明は泉のそばに腰をおろす。待つしかなかった。
(泰明…)
泰明も迷っているのだろうが、自分もまた迷っているのだと、晴明は心の片隅で思った。